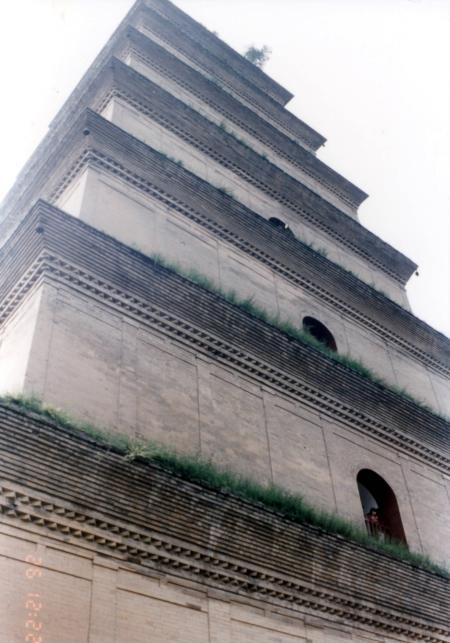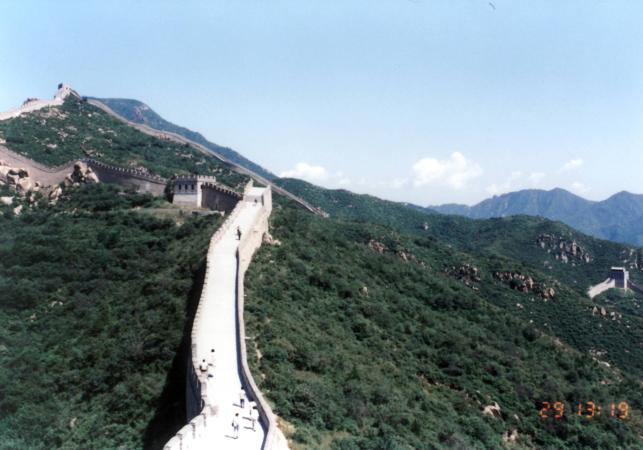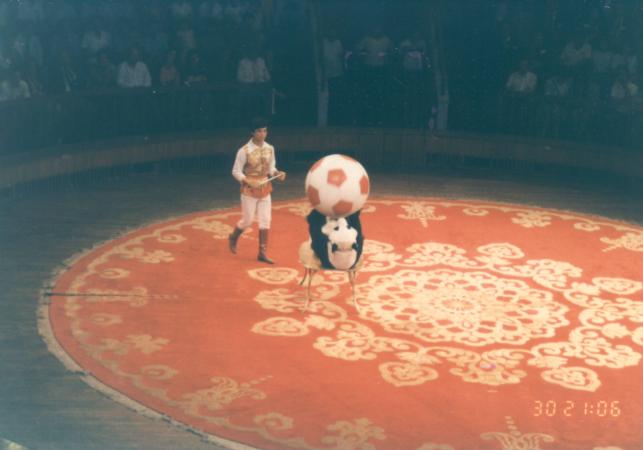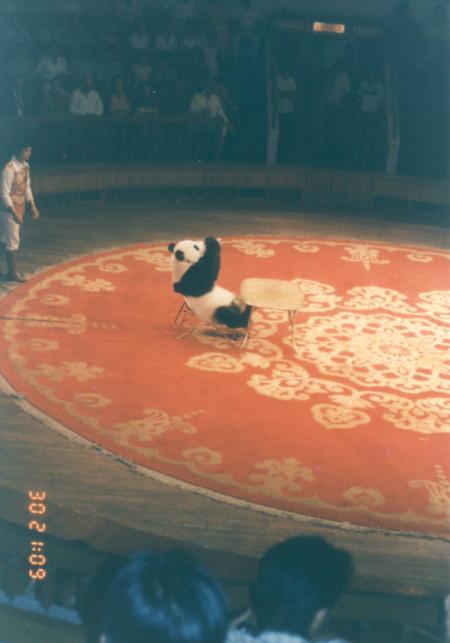| 前訪問地発 |
路 |
当訪問地着 |
訪問地 |
| 出発 |
日本 |
大阪 |
| 20日09:50 |
 |
12:15 |
香港 |
香港 |
| 22日 |
| 23日08:15 |
 |
11:50 |
中国 |
広州 |
| 24日11:00 |
 |
13:10 |
西安 |
| 26日20:35 |
 |
27日16:45 |
北京 |
| 30日09:35 |
 |
11:35 |
上海 |
| 31日01:25 |
 |
06:10 |
杭州 |
| 2日07:25 |
 |
12:50 |
上海 |
| 3日15:00 |
 |
5日12:20 |
日本 |
神戸 |
| 訪問地 |
宿泊先 |
単価 |
泊 |
| 香港 |
香港 |
La Chine Lodge |
HK.$ |
75 |
2 |
| YMCA International House |
HK.$ |
181 |
1 |
| 中国 |
広州 |
華僑酒店 |
CN.\ |
22 |
1 |
| 西安 |
解放飯店 |
CN.\ |
45 |
2 |
| 北京 |
燕京飯店 |
CN.\ |
57 |
3 |
| 杭州 |
杭州飯店 |
CN.\ |
106 |
2 |
| 上海 |
浦江飯店 |
CN.\ |
20 |
1 |
| 国名 |
通貨 |
為替 |
生活 |
食料 |
交通 |
教養 |
娯楽 |
| 香港 |
HK.$ |
18.1円 |
114.60 |
239.90 |
230.90 |
2 |
0 |
| 中国 |
CN.\ |
34.6円 |
59.55 |
307.23 |
797.92 |
0 |
70.10 |
| 日本 |
JP.\ |
1.00円 |
0 |
2,320 |
0 |
0 |
0 |
| 通貨計 |
JP.\ |
1.00円 |
4,132 |
17,285 |
31,776 |
36 |
2,425 |
| 国名 |
住居 |
土産 |
支出計 |
円換算 |
日 |
日平均 |
| 香港 |
331 |
34 |
952.40 |
16,605 |
3.3 |
5,032 |
| 中国 |
515 |
367.70 |
2,117.50 |
60,528 |
12.2 |
4,961 |
| 日本 |
200 |
12,000 |
14,520 |
2,520 |
1.5 |
1,680 |
| 通貨計 |
23,999 |
25,334 |
− |
79,652 |
17.0 |
4,685 |
(注)円換算と日平均は土産費を除く。
|